まずは相談してみる
「課題の解決方法がわからない」「リネアでできることを知りたい」などお気軽にご相談ください。


プラント事業を営むお客様の品質管理部門より、「社内に蓄積された多数の事故事例を、ITやAIを用いて有効活用できないか」とのご相談をいただきました。
関係部署へのヒアリングを通じて、検索に関するさまざまな課題やニーズが明らかになりました。特に、新たな事故が発生した際には、過去の類似事故をすぐに見つけたいという要望が多く寄せられました。また、事故データは、事故の整理や再発防止策の評価といった業務にも活用したいというニーズがありました。それらを支える基盤として、効果的な検索の仕組みが不可欠であると考えられました。
一方で、データベースは特定業界の事故事例で構成されており、固有の用語が多く使われているうえに文章表現も似通っているため、従来のキーワードベースの検索では、必要な情報にたどり着きにくいという声も多く聞かれました。
業務で蓄積された過去の事故情報を有効活用するために、「検索者の検索意図を適切に汲み取り、有用な情報を抽出できる検索」が必要であると考え、システムの構築に取り組みました。
このシステムでは、単なるキーワード一致検索では困難な、類似事故か否かの判断や特定機器の不具合に対する文脈や構造までを考慮した情報検索の実現を目指しました。
PoCから本番システムの構築に至るまで、以下のステップで段階的にプロジェクトを推進しました。
PoCを効率的かつ実用的に進めるため、お客様のクラウド環境上に簡易ウェブアプリを構築し、利用者が検索結果を直接確認・評価できる環境を整備しました。次いで、実際の業務を想定した複数の検索文を準備し、有識者が検索結果の妥当性を評価できる体制を構築。これにより、検索結果の妥当性を定量的に把握できるようになりました。
こうした仕組みによって、現場の実態に即したスピーディーなフィードバックの収集が可能となりました。
PoCでは、以下のような複数の検索手法を検証しました。
標準的な手法は、検索処理は速いものの、事故データは文章が似通っていたこともあり、有識者の期待に応えられるレベルの結果は得られませんでした。 一方、生成AIを活用した検索では、速度こそ劣るものの、検索者の意図を汲み取った検索結果を得ることができ、妥当性の高い情報提示であるとの評価をされました。
これらの検証結果を踏まえ、標準的な検索で候補を絞り込んだ上で、生成AIによる精査を行う多段階型の検索システムを採用し、結果の妥当性と実用性の両立を目指しました。さらに、検索結果の妥当性の向上と将来的な拡張性を目的として、以下のような補完的な取り組みも並行して実施しました。
これらの取り組みにより、検索結果の妥当性と柔軟性を両立し将来的な機能拡張にも対応可能な基盤構築の方向性を決定しました。
PoCで構築したプロトタイプをベースに、UIや機能を整えた本番用の検索システムを開発しました。全社展開を見据え、品質と安定性を確保しつつ、実務での運用に耐えうる仕様へと仕上げています。
システムの裏側では、生成AIやユーザー辞書の連携といった複雑な処理を組み込んでいますが、ユーザーインターフェースはシンプルに設計することで、検索速度や操作性といった実用面での使いやすさも考慮しました。
また、PoCの過程で挙がった新たなアイデアを継続的に検証できるよう、新機能専用の検証画面を別途用意。専任の担当者が新機能を試用・評価できる環境を整え、現場の声を取り込みながら改善を続けられるサイクルを実現しました。
本プロジェクトでは、検索結果の妥当性に加え、速度や操作性にも配慮した実用的な事故事例検索システムを構築しました。全社展開後は日常業務に自然と組み込まれ、過去の事故情報が“活きた知見”として意思決定を支える基盤となっています。
また、本取り組みは、クライアント企業にとって初めての「生成AI × 社内データ」活用事例として注目を集め、今後の業務効率化や他領域への展開も視野に入れた検討が進んでいます。単なる検索システムの導入にとどまらず、組織全体にAIによる知見の活用を促す重要な一歩となりました。
データ事業開拓部 部長 / 博士(工学)

株式会社リネア入社後、非金融業界を中心にデータドリブンなアプローチによる分析業務を担当し、営業からデータ分析まで幅広く携わっている。ラボ契約など多様な契約形態の経験を通じて業務理解とドメイン知識を深めながら、課題解決に向けた提案を行っている。業務理解を起点に、構造的なデータ設計・分析を得意とする。
データ事業開拓部 副部長 / 博士(理学)
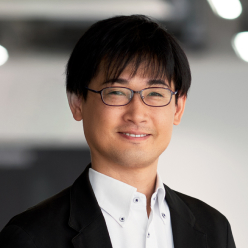
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻にて博士号を取得後、国内外の研究機関にて素粒子論的宇宙論の研究に従事。株式会社リネアに入社後は、非金融業界を中心にデータ分析業務に携わる。データ分析からAIモデル開発までを一貫して行える技術力を強みとしている。
アプリケーション開発部 システムエンジニア / 博士(コンピュータ理工学)

会津大学大学院コンピュータ理工学研究科 コンピュータ・情報システム学専攻にて博士号を取得後、株式会社リネアに入社。高い技術力を活かし、アプリケーション開発を中心に、データ分析やAI開発まで幅広く担当。プロジェクトマネジメントにも携わり、技術領域だけでなくお客様とのコミュニケーションや折衝にも強みを持っている。
市場動向やお客様社内のデータを基に、売上やコスト、成長可能性などを予測。経営・組織・投資の意思決定を支援します。
お客様向けの詳細事例や概算費用は個別にご案内可能です。お気軽にお問い合わせください。